

【2024年度版】これからの採用ブランディング!成功事例を踏まえて進め方を徹底解説!

採用ブランディングは魅力的な「働く場所」として、自社を求職者にアピールする取り組みの一つです。就職・転職市場が求職者優位の「売り手市場」が進む中、優秀な人材を自社に引き入れる戦略として注目されています。
この記事では採用ブランディングの成功に必要なポイントがわからない担当者様に向けて、タカヨシの成功事例や具体的な進め方など、最新情報を交えてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
採用ブランディングとは?

「ブランディング」とは独自のブランドを作り、信頼や共感を通じて自社の価値向上や他社との差別化を目指すマーケティング戦略です。
採用ブランディングはブランディングのなかでも、自社の理念やビジョンや社風、働き方などを戦略的に発信し、求職者に「この会社で働きたい」と思ってもらうための取り組みを指します。
言い換えると、企業を「働く場所」としてのブランド化していく活動とも言えるでしょう。
採用ブランディングは、時間をかけて取り組む必要がある長期的な施策です。しかし、自社にとって必要な人材を獲得し、組織を活性化するためには有効な手段と考えられています。
人材獲得競争を勝ち抜くためには、自社に合った採用ブランディングを構築すること。そして、より多くの人に魅力を感じてもらえる働き場所を創っていく、企業のファン化が求められています。
また、採用ブランディングと似た言葉に、「採用広報」があります。
採用広報とは自社で働くイメージをもってもらうために、企業が自社について情報発信することです。採用ブランディングは「イメージづくり(ブランディング)の活動」を行うという点で、少し意味が異なります。
ブランディングの種類
「ブランディング」と言っても、その種類は多岐にわたります。
- •インナーブランディング:企業理念やビジョン、価値観などを社内で共有し、社員に共感や愛着心を促すブランディング
- •アウターブランディング:顧客や取引先、投資家、一般消費者など社外を対象としたブランディング
- •リブランディング:時代の変化や情報の流れに対応しながらブランドの訴求ポイントやブランドコンセプトなどを変えるブランディング
今回紹介する採用ブランディングはアウターブランディングの一種です。採用ブランディングは、求職者に対して企業の魅力をアピールする活動であると同時に、企業全体のイメージを向上させるための活動でもあります。
関連記事:ブランディングとは?成功事例から学ぶポイントと注意点を解説!
採用ブランディングを実施する目的

なぜ採用ブランディングを実施する必要があるのでしょうか?実は、採用ブランディングには、以下の3つの大きな目的があります。
企業の知名度を上げて応募者を増やす
求人情報だけでは、優秀な人材の目に留まらないこともあります。しかし、採用ブランディングによって企業の魅力を効果的にアピールできれば、優秀な人材との出会いの機会を増やすことが可能です。
採用広告やエージェントの利用には多額の費用がかかります。採用ブランディングによって企業の魅力を広く知ってもらえれば、応募者数を増やし、採用コストの削減も期待できるでしょう。
採用ミスマッチを防ぐ
単に優秀な人材を集めても、企業にマッチしなければ以下のような問題を引き起こします。
- •早期離職による採用コストの増加
- •組織の活性化の阻害
- •企業イメージの悪化
採用ミスマッチを防ぐためには、求職者に自社の企業理念や社風、働き方などを正しく理解してもらうことが重要です。
採用ブランディングで企業情報を積極的に発信すると、以下のような効果が期待できます。
- •求職者が応募前に企業を深く理解できる
- •入社後のギャップが少なくなる
- •マッチ度の高い人材を採用できる
- •早期離職のリスクを減らせる
求職者に企業様の価値観や社風などを理解してもらうことで、安定的な経営や事業拡大に繋がります。
エンゲージメントと従業員の満足度を高める
採用ブランディングによって、企業が外部から高く評価されていることが伝わると、従業員は自社の仕事に誇りを持つようになります。
「この会社で働く一員で良かった」と従業員が感じると、離職率の低下やモチベーションアップにも繋がるからです。
また、従業員の満足度が高いと、仕事のパフォーマンスも高くなります。すると必然的に、顧客や取引先など、外部からも良い評価を受けるように。結果的に、社会からの自社の評判が高まるのです。
効果的な採用ブランディングが行えると、従業員のエンゲージメントと満足度が高まって、このようなビジネスの好循環が生まれます。
競争優位性を確保する
採用ブランディングによって、他社にはない自社の魅力を伝えられれば、競合他者との差別化を図れる可能性があります。
「自社にしかない働き方」や「独自の福利厚生制度」などを求職者に理解してもらえれば、「この企業で働きたい」という、強い決め手になるかもしれません。
特に競争が激しい業界や専門職では、人材獲得競争に巻き込まれないことが重要です。採用における競争優位性を確保できれば、唯一無二の存在として、求職者に認知してもらいやすくなるでしょう。
採用ブランディングが注目される背景

なぜ近年、採用ブランディングが多くの企業で注目されているのでしょうか。主な背景を3つご紹介します。
企業が選ぶ時代から選ばれる時代に
少子高齢化による労働力人口の減少は、深刻な人手不足を招き、採用市場を激化させています。従来の求人広告やエージェントによる採用では、優秀な人材を獲得することが難しくなっているのです。
厚生労働省の調査によると、労働力人口は年間約50万人のペースで減少しており、2035年には約6210万人まで減少すると推定されています。一方、欠員率はコロナ禍を除いて上昇傾向にあり、人材獲得競争は激化。この労働力不足の問題が自然に解決に向かうことは容易ではありません。
人材獲得競争は今後も激化すると想定されます。このような状況下で、求職者から選ばれるには、自社の強みや魅力を明確に伝え、差別化することが重要です。そこで注目されているのが、採用ブランディングです。
採用ブランディングを活用し、ターゲットとなる求職者に響くようなメッセージを発信することで、採用活動を成功に導けます。
※参考:令和5年上半期雇用動向調査結果の概況|厚生労働省
インターネット・SNSの普及
インターネット・SNSが普及したことも、採用ブランディングが注目され始めたきっかけの一つです。
総務省の調査によると、2022年のインターネット利用率(個人)は84.9%。日本のソーシャルメディア利用者数は、2022年の1億200万人から2027年には1億1,300万人に増加すると予測されています。つまり、インターネットやSNSの利用はもはや、人々の生活から切り離せないものになっているのです。
情報発信手段の多様化は、採用ブランディング活動にとっても、追い風となる要素がいくつかあります。
例えば、情報発信の自由度が高くなる点はその一つです。就職情報誌や就職イベントなどの従来の手段と異なり、WebサイトやSNSであれば、時間や場所の制約を受けることなく、自由に情報を発信できます。
ターゲットとなる求職者に合わせた情報発信が可能になる点も追い風になる要素です。例えば、若者向けの求人であれば、InstagramやTikTokを活用するなど、最適なプラットフォームを選択できます。
一方で、情報発信手段の多様化は、採用ブランディング活動にとって課題となる点もいくつかあります。
例えば、インターネット上には、不正確な情報や誹謗中傷などが拡散される可能性があります。企業は、自社の正しい情報を発信し、誤解を招かないように努めることが必要です。
求職者あるいは現従業員が、クチコミサイトやSNSに自由に自社のことを書き込めるため、イメージコントロールが難しくなります。企業は、口コミサイトやSNSを定期的に監視し、常に自社の評判に気を配り、必要に応じてコメントや投稿に対して返信する対策が求められます。
求人者の仕事選びの価値観の変化(転職希望者・Z世代)
近年、社会に出て働く世代の中心となったZ世代(1990年代後半~2000年代生まれ)の価値観は、従来の世代とは大きく異なると言われています。この価値観の多様化は、採用活動にも大きな影響を与えています。
リクルートマネジメントソリューションズが行った調査によると、仕事をするうえで重視したいことトップ2は「成長」(28.8%)と「貢献」(26.7%)。「競争」(2.4%)は昨年に続き最下位という結果でした。これは、お互いに助け合う職場や個性を尊重する職場を望む割合が増えている傾向を示唆しています。
つまりこの結果は、個を活かして活躍できない職場だと受け取られると、優秀な人材の獲得が難しくなっていると言えるでしょう。
Z世代にとって、仕事における貢献実感ややりがいは、人それぞれ多様化しています。従って、企業は単に「仕事を通して社会貢献できる」とアピールするのではなく、具体的な事例や制度などを示すことがポイントです。求職者がどのような貢献や成長、やりがいを実現できるのか、明確に伝えましょう。
では、Z世代に向けた採用はどう行えば良いのでしょうか。
一つ目のポイントは多様な価値観を受け入れることです。従来の画一的な価値観ではなく、まずは一旦、Z世代の多様な価値観を受け入れてみましょう。
個人の成長を支援することもポイントです。Z世代は、個人の成長や自己実現を重要視しています。研修制度やキャリアパスなど、個人の成長を支援できる体制を企業側が整えると良いでしょう。
Z世代の価値観の多様化は、採用活動にとって大きな課題であると同時に、新たなチャンスでもあります。企業は、Z世代の価値観を理解し、それに対応した採用活動を行うことで、優秀な人材を獲得できる可能性が高まるでしょう。
※参考:新入社員意識調査2023|リクルートマネジメントソリューションズ
採用ブランディングの進め方

採用ブランディングは具体的に、どのような手順で行えば良いのでしょうか。進め方を順を追って解説します。
ターゲットを設定する
採用ブランディングにおいて、ターゲット設定は非常に重要です。ターゲットを設定する際にはまず採用要件を作成しましょう。採用要件とは、求める人材のスキルや経験、資格などの条件をまとめたものです。
続いて、作成するのが「採用ペルソナ」です。採用ペルソナとは、採用要件を満たした架空の人物の詳細なプロフィールを想定したもの。採用ペルソナを作成する際には、以下の点を意識しましょう。
- •年齢
- •性別
- •学歴
- •職歴
- •スキル
- •経験
- •価値観
- •ライフスタイル
- •情報収集の方法
採用ペルソナを具体的に設定すると、次のようなメリットがあります。
- •求職者に共感してもらえるメッセージを発信できる
- •求職者の興味関心を引くコンテンツを作成できる
- •採用活動のターゲティングを絞り込める
採用ブランディングを成功させるためにも、まずはターゲットを明確にし、そのターゲットに響くメッセージを発信しましょう。
自社の強みを見極める
ターゲットを設定したら、次は自社の強みを見極めます。自社の強みが明確になると、求職者に自社の魅力を効果的に伝えることが可能です。競合との差別化がしやすくなり、採用活動を効率的に進めやすくなるでしょう。
自社の強みを見極めるには、次の3つを分析します。
【自社分析】
•業内容や商品、サービス
•どのような社風
•どのような福利厚生制度があるか
•経営陣の特徴
•社員の特徴
•過去にどのような採用活動をしていたか
【競合分析】
•競合他社の事業内容や商品、サービス
•どのような社風か
•どのような福利厚生制度があるか
•どのような採用活動をしているか
•求職者からどのような評判があるか
【市場分析】
•業界全体の動向
•求職者のニーズ
•どのような競合他社があるか
3つの分析で、
•自社の強み
•競合との差別化ポイント
•求職者に訴求できるポイント
を整理できます。これらが明確になると、採用ブランディングの方向性が定まり、より効果的な施策を実行できます。
運用計画を立てる
ターゲットを設定し、自社の強みが明らかになったら、運用計画を立てます。運用計画では、以下の項目を盛り込むことが大切です。
•目標
•ターゲット
•戦略
•施策
•スケジュール
•予算
•担当者
•指標
例えば「1年後には応募者数を20%増加させる」を目標とする場合、ターゲットは新卒大学生、既卒者2年目までの求職者と設定できます。
自社の強みである「革新的な技術力」と「働きやすい環境」を訴求する戦略が立てられるでしょう。
この場合、応募者数や採用単価、入社率なども指標になります。運用計画は定期的に見直し、必要に応じて修正していくことがポイントです。
発信内容を企画する
運用計画が決まったら、発信内容を考えていきます。例えば、個人の裁量で仕事ができる環境の場合は、一人一人の仕事の裁量の大きさの紹介や過去のプロジェクトの紹介などを用いて紹介すると効果的です。
個人が成果を出せるよう、生産性を向上できる取り組みを行っている場合は、自社特有の取り組みの紹介や、個人の生産性に対する想いについて代表者にインタビュー形式で伝えると良いでしょう。
どのような言葉やイメージが求職者の心に響くか、先の自社分析で収集した結果を用いて、情報を絞り込んでみてください。
情報を発信する対象者はターゲット設定の段階で既に決まっているので、そのターゲットに向けて伝える情報を絞り込んでいきます。
一人の担当者が全てを考えるのではなく、何人かのメンバーで案を出しあったり、アイディアを投票したりすることで、より良い企画になります。
発信手段を決定する
続いて、実際にどのように採用ブランディングを行うか、その発信手段を決めましょう。
SNSや採用サイトなど、発信手段は色々ありますが、それを利用するユーザーの年齢層や傾向は下表の通り、媒体によって異なります。
| X(Twitter) | LINE | Tiktok | YouTube | |||
| ユーザー層 | 10〜20代の女性が多い | 20代が多い | 日本最大級のSNS | 10〜20代が多い | 幅広い年齢層 | ビジネス利用の30代が多い |
| 特徴 |
・画像や動画などビジュアル訴求しやすい商材向き ・ECサイトと連携しやすい |
・カジュアルな短文コミュニケーション ・拡散力が高い |
・1on1コミュニケーションに最適 ・スタンプやショップカードなどの独自機能がある |
・ユーザーの好みや履歴に応じてリーチできる |
・古い動画も検索して見てもらえる可能性がある ・SEO(検索エンジン最適化)に強い |
・実名登録でリアルなつながり重視 ・年齢や性別等のターゲティング精度が高い |
自社にマッチする人材が集まるかは、どの発信手段を選ぶかに左右されます。従って、業界や企業の特徴に合わせて決定すると、希望する人材とマッチしやすくなるでしょう。
ターゲットとなる人材がどのような媒体で情報収集しているのか分析すると、自社にマッチした人材が集まりやすくなります。
文字や文章だけでなく画像や動画などを用いながら、必要な情報がわかりやすく、印象に残るように発信してみてください。
運用・振り返り
運用と振り返りを繰り返すことで、より効果的な採用ブランディングを行えます。分析を行う際には、次の点に着目しましょう。
- •応募者の属性
- •応募経路
- •採用担当者への評価
これらを分析すると、自社が求めるターゲットが集まっているかを確認できます。
不十分な点がある場合は、
•不十分な施策の改善
•新しい施策の導入
•ターゲットの設定の修正
などを行って、改善を図りましょう。運用の結果は、社員と定期的に共有することも重要です。結果に応じて、研修の実施や、リーフレットの配布などを行って、情報を共有してみてください。
運用と振り返りを繰り返すことで、自社の魅力を効果的に伝え、優秀な人材を獲得できます。
採用ブランディングに活用できる手段

採用ブランディングに活用できる手段には何があるのでしょうか。代表的な手段を4つ紹介します。
自社採用サイト
自社の採用情報に特化した採用サイトはターゲットを求職者のみに絞っているため、情報が集めやすい点がメリットです。Webサイトを訪れる学生が企業をより身近に感じられる良さもあります。
企業の魅力や採用に対する想いを伝えられるため、企業イメージや内定承諾率の向上も期待できます。
| 特徴 | 企業独自の情報を発信できる |
| メリット | 自社の強みをアピールしやすい |
| デメリット | 集客に時間がかかる |
| 活用例 | 企業理念やビジョン、社風などを詳しく紹介 |
求人媒体サイト
幅広い求職者にアプローチしたい場合は、リクナビやマイナビなどの求人サイトを活用する手段もあります。自社の状況に合わせて、先に紹介した自社採用サイトも併用することで、より多くの優秀な人材にアプローチできます。
求人掲載の費用を抑えたい場合は無料の求人媒体や、求人広告の掲載費用を抑えられる媒体を利用することが可能です。特定の職種に特化した求職者にアプローチしたい場合は、専門性の高い求人媒体に掲載すると良いでしょう。
| 特徴 | 多くの求職者にアプローチできる |
| メリット | 採用コストを抑えられる |
| デメリット | 採用競争が激しい |
| 活用例 | 求人情報を掲載 |
SNS(Instagram、X、Facebookなど)
InstagaramやX(Twitter)、FacwbookなどのSNSを使って、求職者に採用に関する情報発信ができます。
企業が発信した情報は、フォロワーだけでなく、フォロワーのフォロワーへと拡散していくため、多くの求職者にリーチできます。
求職者との双方向的なコミュニケーションができる点もSNSの特徴です。企業は求職者の質問に答えたり、コメントをやり取りしたりすることで、求職者と信頼関係を築けます。
求人広告などに比べ、費用を抑えながら多くの求職者にアプローチできる点もメリットです。画像や動画を使って企業の魅力を伝えられるので、求職者は企業の雰囲気や社風などをよりリアルに理解できます。
| 特徴 | 拡散力、双方向的なコミュニケーション、コスト、魅力発信 |
| メリット |
・ユーザと信頼関係を築ける ・費用を抑えながら採用活動ができる ・企業の魅力を効果的に伝えられる |
| デメリット |
・炎上リスクがある ・担当者の負担が大きくなる ・長期的な視点で取り組む必要がある |
| 活用例 |
・求人情報やイベント情報の発信 ・質問への回答、コメントへの返信 ・ターゲット層に絞った広告配信 ・動画コンテンツ ・会社紹介 |
企業説明会などのイベント
採用ブランディングは、WebサイトやSNSなどのオンラインツールだけでなく、対面のイベントも使います。例えば企業説明会やセミナーなどです。このような対面式のイベントでは、企業の代表や人事・採用担当者などが、自社に興味をもってくれた人々と直接会ってアプローチできます。
リアルに接する機会が増えると、求職者が会社に親近感を抱き、就職先・転職先の候補に入れる可能性があります。
イベントを成功させるには、インターネットを介した発信方法との併用が不可欠です。オウンドメディアやSNSなどを活用し、自社のファン化を進めましょう。イベント前には事前に十分に告知して、求職者の目に触れる工夫も重要です。
| 特徴 | テーマや内容を告知し、参加者が集まって交流する |
| メリット |
・企業が求職者と直接会ってアプローチできる ・求職者が会社をより身近に感じられる |
| デメリット |
・長期的な採用ブランディングが必要 ・オンラインイベントと比べて準備に時間がかかる |
| 活用例 |
・業界研究会、座談会 ・会社説明会、インターンシップ、社内イベント |
押さえておきたいポイント
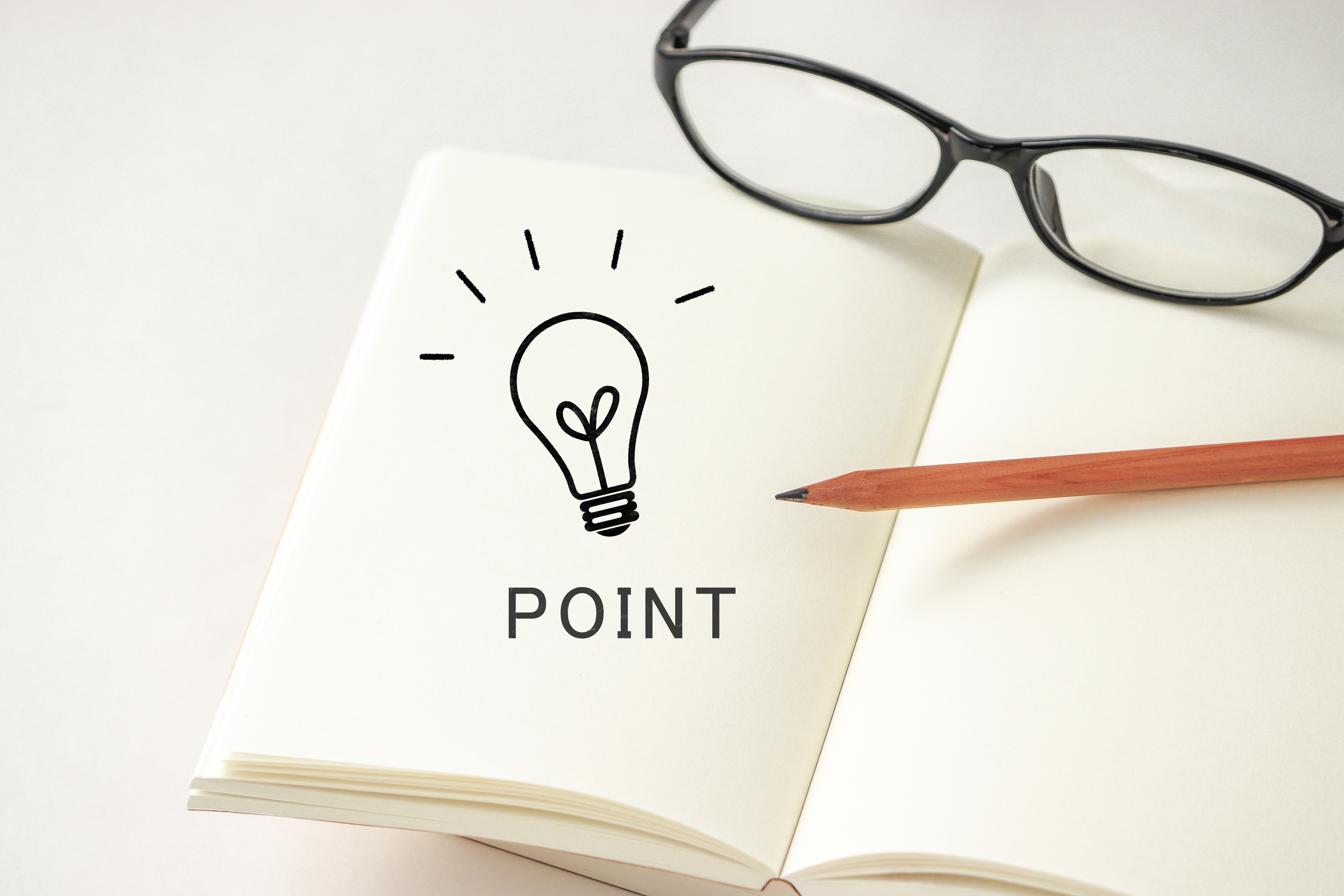
採用ブランディングに取り組む際に押さえておきたいポイントを3つご紹介します。
社内全体で取り組む
採用ブランディングを社内全体で取り組むと、次のような問題を防げます。
- •求職者に伝わるメッセージに一貫性がなくなる
- •入社後に求職者がイメージしていたものと違うと感じてしまう
- •採用活動と社内の風土にギャップが生じる
社内全体で取り組むためには、まず「採用ブランディングの目的や目標」「求職者に伝えたい自社のメッセージ」を社員の間で共有することが大切です。
従業員に採用ブランディングの重要性を理解してもらうと、現場でのギャップが生じる事態を防げます。
採用ブランディングや企業イメージについて、研修を実施することも効果的です。研修は座学やe-ラーニングでもできますが、ディスカッション形式やグループワークなどを行うと、より記憶に残りやすくなります。
成果が出るまでに手間と時間がかかることを認識する
採用ブランディングには即効性がないため、中長期的な視点で取り組む必要があります。認知向上や企業イメージの浸透には1年以上はかかると理解しておきましょう。
短期的な結果を求めて、次のような戦略を展開すると、逆効果です。
- •不透明で短絡的なメッセージを発信する
- •場当たり的な施策を展開する
- •十分な検証を行わずに施策を実行する
結果を焦ると、最悪の場合、企業イメージを損なう可能性もあります。
- •定量データに基づいて効果を分析する
- •分析結果に基づいて改善策を講じる
- •計測可能な指標を設定し、その動向を注視する
このような、長期的な視点に立って、着実に取り組む姿勢が大切です。
継続的な情報発信を行う
継続的な情報発信をすると、次のような効果が期待できます。
- •求職者に自社の存在を知ってもらう
- •自社の魅力を理解してもらう
- •入社後のイメージを具体的に持ってもらう
- •求職者の興味関心を高める
- •企業イメージを向上させる
また、継続的な情報発信は求職者に企業の誠実さや安定感、信頼感を与える効果もあります。
情報発信する際は、
- •ターゲットとなる求職者のニーズに合わせた内容にする
- •自社の強みや魅力を分かりやすく伝える
- •新鮮で興味深い内容にする
- •定期的に更新する
などがポイントです。採用ブランディングを成功させるためにも、継続的な情報発信を行いましょう。
タカヨシの採用支援30年の実績・成功事例
株式会社タカヨシは、新潟県で30年以上前から採用支援を行っている企業です。
高卒採用情報誌の発行から始まり、近年ではマイナビ正規代理店として、採用ポータルサイト「マイナビ」や採用パンフレット、採用ホームページなど、多様なツールを活用した採用ブランディング支援を提供しています。
タカヨシの強みは、3つの柱に集約されます。
- 1.豊富な経験とノウハウ
- 2.多彩な採用ツール
- 3.地域密着型のパートナーシップ
タカヨシはこれまで、30年以上の経験と実績に基づき、お客様の採用課題を的確にヒアリングし、最適なソリューションを提案してきました。
初期の情報発信からエントリーの窓口まで、採用活動に必要なあらゆるツールをワンストップで。新潟県に唯一のマイナビ正規代理店として、地域に根差した採用支援を行っている点が強みです。
タカヨシの主なサービス内容は以下の通り。
- •採用課題のヒアリング~ご提案~実行
- •課題の共有
- •採用ターゲット策定
- •採用施策スケジューリング
- •各種ツールで効果的な採用ブランディングを実現
- •採用担当者向けお役立ちセミナーを開催
まず、お客様の採用目標と課題をヒアリングし、目標達成のための具体的なプランをご提案。スケジュールに合わせ、必要なツールの作成とイベントの実行を行います。
その後、採用活動における課題を共有。解決に向けた方策を検討しながら、採用ターゲットを明確にし、効果的な採用活動を行います。
採用活動のスケジュールを策定では、スムーズな実施をサポート。マイナビ、採用パンフレット、採用ホームページなど、様々なツールを適切なタイミングで提供します。採用担当者向けのセミナーや勉強会を開催し、最新の採用情報やノウハウを提供することも可能です。
就活生向けの企業紹介リーフレットを制作した事例では、表紙デザインとキャッチコピーで企業の魅力を表現。冊子内にAR機能を導入することで、学生の興味関心を高めました。
その他にも、タカヨシでは貴社の採用活動を成功に導くための最適なパートナーとして、数多くの採用ブランディングに携わった実績があります。
まとめ
採用ブランディングは企業イメージの認知向上や離職防止などのメリットがあります。今回紹介したタカヨシの成功事例や押さえておきたいポイントなどを参考に、自社にとって最適な採用ブランディングを検討してみてはいかがでしょうか。
採用ブランディングで着実に成果を上げたい場合は専門的な知識やノウハウをもつ企業からアドバイスを受けることをおすすめします。タカヨシでは経験豊富なスタッフが採用ブランディングに関するアドバイスを行っていますので、この機会にぜひご相談ください。




